はじめに
今日は近年投資のメインストリームといっても過言ではない仮想通貨について見ていきましょう。
仮想通貨はここ十数年で莫大な価格上昇を示しています。と同時にボラティリティも非常に大きくなっています。この原因は、中国における仮想通貨取引の取り締まり強化、環境問題、および増税が挙げられるでしょう。一方で政府や中央銀行などの公的機関が仮想通貨を作ることにより、より適した市場を開発することもアイディアとして出ています。
今日は、投資家なら一度は考えたことがあるであろう、「仮想通貨をポートフォリオに組み込むべきなのか?」という疑問にDr. David Kellyが答えてくれました。
細胞くんと一緒に仮想通貨の歴史、特徴、利点、そして欠点を学び、仮想通貨への理解を深めて未来に備えましょう。
対話スタート
司会:すでにリスナー(読者)はご存知かもしれませんが、まずは仮想通貨がどのように始まったのか、その歴史から教えてもらってもいいですか?
David:Bitcoinは2008年10月に発表された1本の論文から取引が開始されました。著者はサトシ・ナカモトと名乗っており、彼の目的は中央銀行や政府に頼らないオンライン決済システムを開発することでした。
Bitcoinは非常にユーザーフレンドリーで、ソフトウェアをインストールするだけで簡単に購入できます。また、偽造が非常に困難であることも特徴です。
司会:Bitcoinの開発以降、同様のBlock chain technologyを使用した仮想通貨が何千と生み出されてきましたが、これらの違いは何でしょうか?
David:すべてに共通して言えることは、誰でも簡単に取得できるということです。違いは多岐にわたります。あるコインは、Bitcoinが抱える問題に着目していたり、通貨の使用を減らすことで環境問題に取り組むことを目指していたり、より複雑なセキュリティを使っていたりなど、仮想通貨ごとに特徴があります。
司会:仮想通貨の人気が急増しているのは分かるのですが、本当に日常の決済で使われる未来が来るのでしょうか?今後仮想通貨が直面するであろう問題は何ですか?
David:日常で使われるようになる未来はちょっと難しいと考えています。主に2つのハードルがありますが、1つ目は通貨には安定性が求められるということです。これは仮想通貨の魅力と完全に矛盾します。人々がBitcoinを求めるのはボラティリティが高く、大きな利益を得られるチャンスがあるからです。Bitcoinのボラティリティが減り、より安定性が増したとすれば、保有者は激減するでしょうから。
2つ目のハードルは、仮想通貨を使用できるお店の数ですね。クレジットカードを使えるお店がニューヨークに2軒しかなかったとすれば誰もクレジットカードを持ちませんよね?それと同じで、決済に使えるお店が少なければ仮想通貨が日常的に使われることはないでしょう。
司会:解決法はありますか?
David:いくつかあると思います。まずBitcoinが抱える問題の1つは、決済スピードの遅さです。これに関してはおそらく技術者たちが目下解決にいそしんでいると思います。あとは。やはり現物がないという点ですね。多くの人たち、特に高齢者は実体のないものを買い物に使い、かつその価格が上下するという感覚について行けないと考えています。
司会:分かりました。では次に投資の観点から仮想通貨を見ていきたいと思います。仮想通貨で巨額の利益を上げている人がいるために、仮想通貨が非常に魅力的に見えている投資家もいると思います。我々は仮想通貨をポートフォリオに組み込むべきですか?
David:ポートフォリオの中身を分散させることは、様々なリスクに対応するうえで非常に重要です。そういった面では仮想通貨をポートフォリオに組み込むことに意味はあると思います。ただし、購入を考える際には以下の3つのことに注意してください。
①期待するリターンはどれほどなのか。②ボラティリティの高さはどれほどなのか。③組み込んだ際のポートフォリオ全体のボラティリティは許容範囲なのか。というのも、すでにポートフォリオにボラティリティの高い資産が含まれているのであれば、異常なボラティリティを持つ仮想通貨を組み込むことはリスクの増加につながります。
株式や債券の価格が減少した際にBitcoinの価格が上がるために、全体のボラティリティを減らすことにつながると言う人がいますが、この関係は未だに証明されていません。仮想通貨はまだ資産として地位を確立してからの期間が短いため、研究材料に乏しいというのが現状だからです。
以上のことから現時点では、仮想通貨を人に勧めるのは非常に難しいと考えています。
司会:資産全体の1~2%という小規模で加えるのはどうですか?
David:宝くじを買う感覚で買いたいというのであれば良いのではないでしょうか。しかしリタイア後やアーリーリタイアのための資産形成に組み込みたいというのであれば、答えはNoです。ポートフォリオ内の仮想通貨の組み込み率はゼロ%にしましょう。
司会:分かりました。仮想通貨が魅力的だという一方で、テックバブルや不動産バブルなどの世界恐慌につながるバブルである可能性があるのではないかという意見もありますがどう考えていますか?
David:その可能性は低いでしょう。確かに仮想通貨の価格はここ数年で急上昇していますが、世界全体の金融資産としてはまだまだ小規模だからです。例えばアメリカ国内の不動産の時価総額は145兆ドルですが、仮想通貨の全体の時価総額は1兆ドルとなっています。
2000年のテックバブルを思い返してみると、多くの企業がネットワークを創り出すために設備投資をしていました。そのおかけでテック企業に対する需要が高まり、テック企業の株価が急上昇しました。しかし仮想通貨においては需要の高まりは見られていません。
以上のことから、将来起こりうるかもしれませんが、今は仮想通貨の価格が暴落したとしても世界恐慌にはつながらないでしょう。
司会:仮想通貨でもう1つ懸念されているのがESGリスクです。Bitcoinマイニングにかかるエネルギーが環境への配慮を怠っているのではないかという指摘ですね。
David:ビットコインは、一定期間ごとに、すべての取引記録を取引台帳に追記します。その追記の処理には、ネットワーク上に分散されて保存されている取引台帳のデータと、追記の対象期間に発生したすべての取引のデータの整合性を取りながら正確に記録することが求められます。
結論から言えば、暗号資産(仮想通貨)業界における「マイニング」とは、ビットコインに代表される暗号資産(仮想通貨)の売買取引などを記録する作業にコンピューターを使って貢献し、その対価として新たに発行される暗号資産(仮想通貨)を得ることを指します。
このマイニングにかかるエネルギー消費は1~2つの国のエネルギー消費と同等だと言われており、かなりクレイジーですよね。
他にも問題があり、それは富の偏りです。アメリカでは資産の多くが、上位数%の人々で保持されているように、同様の現象が仮想通貨界隈でも起きています。仮想通貨を多く持っている人は、事業に成功し雇用を生み出したわけでもなければ、世界に貢献したわけでもありません。ただ、開発初期に仮想通貨を持っていたというだけの人々に富が偏っています。
マネーロンダリングや、犯罪による収益も仮想通貨で行われることで、摘発されにくいという次章も報告されています。
全体的に見て、ESGリスクは非常に高いと言えるでしょう。
司会:エルサルバドルでBitcoinを通貨として公的に使えるようになりました。エルサルバドルでは、アプリを通じて国から支給されたBitcoinを利用して様々なサービスやグッズを購入することができます。これについてどう考えていますか?
David:良いことはないでしょうね。Bitcoinはもちろん一夜にして倍の価格になることもありますが、逆に減ることもあります。定期的にもらえる給料の価値が、明日には10%減っているかもしれませんし、半分になっているかもしれません。
エルサルバドルの国民はUSドルか、ユーロか円を持つことで政府に対抗するべきでしょう。そもそもBitcoinはこれらの現実通貨からの”寄付”により成り立っているのですから。
司会:その通りですね。少し話を変えましょう。夏に中国が仮想通貨に関連する事業を全面禁止にすると発表しましたが、中国の流れに続く国家は現れますか?
David:環境への配慮と国家の統治という観点では、有り得ると考えています。仮想通貨のマイニングには先ほども言ったように大量の電力を使うために、これを歓迎する国家は現在ありません。また国民が自国の通貨以外の仮想通貨で取引を行うということは、自国の通貨の価値の低下や、政策支援の混乱にもつながるために統治の観点からも歓迎されませんからね。
司会:ありがとうDavid。全体を通して、仮想通貨を保有することは投資家には勧められないという今日の内容でしたが、最後に仮想通貨に関連するポジティブな面を教えてもらえますか?
David:もちろんです。まず、仮想通貨の取引に使われているブロックチェーンテクノロジーは素晴らしい技術です。この技術の発展により、オンラインでより安全に送金ができるようになりました。今後も色んな経済局面で利用される技術となるでしょう。
また中央銀行にプレッシャーをかけるという点においても素晴らしい働きをしてくれました。今は簡単にドルを使って円口座やユーロ口座に簡単に送金することができますが、これは仮想通貨の発展が中央銀行を脅かしたからです。各国の中央銀行が他国の通貨建ての口座への送金を容易にする努力を怠れば、国民は仮想通貨を保持することになっていたでしょう。
司会:今日はありがとうDavid。
考察
いかがだったでしょうか。Bitcoinを公的通貨として使い始めたエルサルバドルに続く国家が現れるのか、はたまた仮想通貨取引を全面禁止にした中国に続く国家が現れるのか、今後の世界経済の動向が楽しみですね。最後に、取引やマイニングにかかる電力消費量に関する表を見つけたのでシェアしたいと思います。
1回の仮想通貨取引にかかる消費電力の比較
この表で見ると、如何にBitcoinが電力を派手に消費しているかがわかりますね。ちなみに日本の一般的なアパートの一室で、エアコンを使わずに一日を過ごした際の消費電力が7.7kwhである(参照:電力計画.com)ため、その100倍の電力が1回のBitcoin取引で消費されていることになります。
現在ヨーロッパだけではなく中国やアメリカもSustainability(持続性)を重視した政策に転換を始めたために、Bitcoinの消費電力削減は急務である可能性が高いと考えられます。続報があればまたブログ記事にします。
金融商品は安く購入して、高く売却する。ただそれだけ。今日も皆さんが楽しい投資ライフを送れますように。
*上記に含まれるコンテンツの一部はPodcast "Insights NOW"を和訳したものであり、情報提供のみを目的としております。また内容は作成時に入手可能な情報に基づくものあり、読者様の財務状況や投資目的を考慮しておらず、内容が適さない可能性があることにご留意ください。
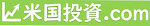




コメントを投稿
コメントを投稿